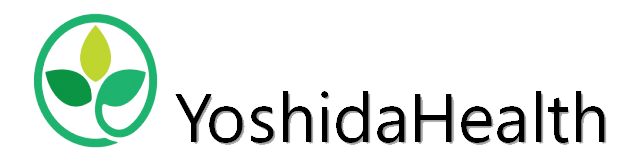もくじ
1. はじめに
「食べるな危険・・」などという市民の不安を煽る書籍や、食品添加物があたかも毒物かのように描かれた週刊誌やネット記事により、
危険重視の「確証バイアス」に陥った消費者たちがSNSで食に関する誤情報を拡散してしまうインフォデミックは長年の社会問題です。
「天然食材=安全」・「化学合成の添加物=危険」という消費者のリスク誤認は、食品事業者による「無添加マーケティング」により、
さらに助長される悪循環がずっと続いていました。
実は、食品安全行政も食品添加物の安全性データを専門書に載せ、市民公開講座やホームページでも安全情報を継続的に発信していましたが、残念ながら「食品添加物は使用基準のもと安全」という科学情報は、危険重視の消費者の琴線に当たらず、市民の「確証バイアス」は解消していません。
2.ファクトチェックが必要な理由
この社会問題に対抗するために、われわれSFSSが注目した取組みが「ファクトチェック」です。
「ファクトチェック」とは、社会に広がっている情報・ニュースや言説が事実に基づいているかどうかを調べ、そのプロセスを記事化して、正確な情報を人々と共有する営みのことであり、一言でいえば「真偽検証」です。1)
 すなわち、「食品添加物は安全です」という“大人しい”科学情報ではなく、
すなわち、「食品添加物は安全です」という“大人しい”科学情報ではなく、
「食品添加物のリスクに関する不安煽動記事は誤り」というファクトチェック情報を世に発信することで、
「本当に危険なのは誤情報だ」と市民に認識してもらうことが重要と考えたわけです。
「大岡越前」と「悪代官」の二項対立のように、「ファクト」と「フェイク」の対立構図を明確な結論として情報発信すると、何が科学的に正しいのかわかりやすく、市民の批判的思考+リスクリテラシーが醸成されるのでしょう。
3.ファクトチェック・ガイドライン
2017年に日本ではじめて立ち上がったファクトチェック推進団体「ファクトチェック・イニシアティブ(FIJ)」(https://fij.info/)にて、筆者自身、創立時より理事をつとめており、国際ファクトチェック・ネットワーク(IFCN)の綱領2)に沿ったファクトチェック・ガイドライン3)を公開しましたが、SFSSでもこのFIJガイドラインに準拠したファクトチェック運営方針を公表しています(概要を一部抜粋):
4.SFSSファクトチェック運営方針4)
<目的>
事実に基づかない科学報道やエビデンスの薄弱な言説によって、市民の健全な生活習慣(とくに食生活・運動習慣・健康管理手法など)や正しいリスク認識による行動判断が脅かされないよう、メディア報道やインターネット上の言説のファクトチェック(真偽検証)を行います。
<対象範囲と選択基準> 中略
<判定基準>
SFSSは、本ファクトチェックの結論として、以下の判定(レーティング)基準を用いて発表します:
| レベル0(正確) | 言説は、科学的根拠が明確な事実に基づいており正確である。 |
| レベル1(根拠不明) | 調査の結果、事実かどうかの科学的根拠が見いだせなかった場合。 なお、科学的根拠を示すべき責任は言説の発信者にあるものとする。 |
| レベル2(不正確) | 事実に反しているとまでは言えないが、言説の重要な事実関係について科学的根拠に欠けており、不正確な表現がミスリーディングである。 |
| レベル3(事実に反する) | 言説は、科学的根拠を欠き事実に反する。 |
| レベル4(フェイクニュース) | 言説は事実に反すると同時に、意図的な虚偽の疑いがある。 |
<訂正方針><組織情報>など 後略
5.「超加工食品」の論文に関する疑義言説のファクトチェック5)
SFSSでは、上記のファクトチェック運営方針にそって、おもに食品安全のリスクに係る疑義言説を対象としてファクトチェック記事を公開しています。その中でも、最近注目されているMonteiro博士らが開発した「NOVA分類」により区分された「超加工食品」と生活習慣病に関わる論文を採り上げた疑義言説をファクトチェックしました。5)
パリ第13大学の疫学調査論文について、「超加工食品」の摂取量が多い人ほどがんの発症率が高かったという結果は理解できましたし、栄養の偏りが大きい人ほど発がんリスクが高いという過去の疫学研究と変わらないとの印象でした。
問題の疑義言説は、この論文結果を曲解して、食品添加物の種類が多い加工食品ほど発がんリスクが高いと評価し、国内の加工食品の発がんリスク・ランキングを実名で発表した週刊誌の記事です。我々は、名指しされた商品への事実無根の信用毀損として、本言説のファクトチェック判定を「レベル4(フェイクニュース)」としました。
6.ファクトチェックを通じて考えるエビデンス情報の利活用のあり方
食のリスク情報に関する疑義言説の特徴は、上述の事例と同様、引用された科学論文のデータ自体は正確=「レベル0(事実)」にもかかわらず、その結論/解釈や一部切り出した見出しが「レベル2(不正確、ミスリード)」であったり、意図的偽情報=「レベル4(フェイクニュース)」である場合が多いことです。MIT-SSMのシナン・アラル教授も、事実と誤情報が混在する「混合型」のフェイクニュースが昨今は増えており、著名な書籍や論文が引用されると市民が騙されやすいと指摘しています6)
最近WHOが、「低カロリー代替甘味料は肥満予防に効果なし」とアナウンスしたようですが、どんなシステマティックレビューをして、このような結論に達したのか危惧するところです。患者さんの肥満予防を指導するのに「カロリーオフ」を薦めていた世界中の医師/栄養士はきっと当惑しているのではないでしょうか。