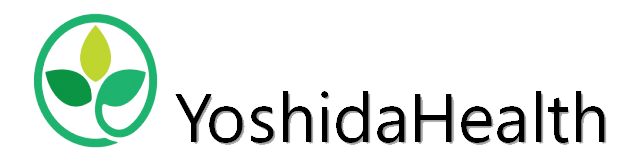■ はじめに
「健康に良い」といわれるさまざまな食品が販売されていますが、広告によるイメージが先行し、不適切な利用方法による健康被害も少なくありません。保健機能食品 (特定保健用食品 (トクホ) 、栄養機能食品、機能性表示食品) であっても同様です。中でもトクホは「国が認めたものだから」という理由で、その効果に過度の期待を抱かれがちです。
効果的にトクホを活用するために、使い方を見直してみませんか。
[注:文中の () 内の数字は末尾に示した参考文献に対応しています。是非参考にしてください。]
■ 特定保健用食品 (トクホ) とは
トクホは平成3年に創設・制度化されました。当時は医薬品と区別をするため、明らかな食品の形態をしていることが必須要件でした (7) が、保健機能食品制度が創設された平成13年以降は、錠剤やカプセル状のものも許可されるようになりました。平成17年からは、条件付きトクホ、規格基準型トクホ、疾病リスク低減表示のトクホといった種類のトクホも認められるようになりました (4) 。

トクホには以下のような特徴があります (4) 。
・食品表示法により定義されている。
・国が製品として有効性や安全性を評価し許可・承認している。
最終製品でその有効性と安全性が評価されている。
・通常の食品には認められていない特定の保健の用途の表示ができる。
保健の用途の表示とは、健康の維持・増進に役立つ、または適する旨の表現を指し、医薬品のような病気の治療や治癒に対する効果の表現は認められていない。
・商品に付けられている「許可証票 (右上図) 」によりトクホであることが明確にわかる。
*トクホの分類は「このデータベースで意味する「健康食品」について」をご覧ください。
■ 利用上の注意
1.利用対象者を確認する
トクホは医薬品ではありません。トクホの効果に過度の期待をしたり、医薬品的な効能を求めたりすると、病気を悪化させたり、適切な治療を受ける機会を失う場合があります (1)。
トクホは健康が気になる人や、普段の食生活に不安を感じている人など、「病気ではない人」を対象として設計されています。利用対象者を正しく理解しましょう。
2.イメージだけで選ばない
トクホは「いわゆる健康食品」と呼ばれる商品に比べて安全性が保証されていると考えられます。しかし、その利用方法が適切でなければ商品に表示されている効果を期待できないばかりか、望ましい生活習慣の妨げになることもあります。
一般に、「トクホは国が認めている」という事実と、期待される作用ばかりが注目され、適切な利用法や利用上の注意などが疎かになりがちです。「トクホは国のお墨付きだから」と絶対の安心感を持ってしまう方もいるでしょう。しかし、「特定保健用食品」という名前の通り、トクホも「食品」のひとつです。トクホは、「消費者にとって、商品を選ぶときの判断材料 (科学的根拠に基づく情報) が、明確に表示されている食品」であり、トクホさえ利用していれば健康になれるというものではありません。
*いわゆる健康食品については「このデータベースで意味する「健康食品」について」をご覧ください。
3.誤った認識で利用しない
たとえば、トクホの中で「体脂肪がつきにくい油」がありますが、食べれば食べるほど体脂肪がつきにくくなるわけではありません。あるトクホの油の有効性を確認した研究では、食事制限をした条件で、「通常の油」と「トクホの油」を置き換えて比較しています (5) 。このように、トクホが持つ作用を最大限に引き出すためには、適切な食生活を送っていることが前提となります。
このため、平成17年に行われた保健機能食品制度の見直しにより、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを」という文言をトクホの容器包装の前面に表示することが義務付けられています。
4.過剰摂取に注意する
トクホには科学的根拠に基づいた期待される効果がありますが、「効果がある」ということは、「望まない作用を起こす可能性がある」ことも意味します。たとえば、「お腹の調子を整える食品」を一度にたくさん摂るとお腹がゆるくなる可能性があります。トクホはたくさん摂ったからといって大きな効果が得られるものではありません。このような注意点は、商品の「摂取をする上での注意事項」などに必ず記載されていますので、利用の際はよく読んで、摂取量や摂取方法に注意しましょう。
「お腹の調子を整える食品」「血糖値が気になり始めた方の食品」「食後の血中中性脂肪が上昇しにくい食品」は、期待される効果は違いますが、いずれも「難消化性デキストリン」を関与成分 (保健機能を有する成分) として含む商品があります。このように、期待できる効果が異なっていても、表示を注意深く見ると、同じ成分であることも稀ではありません。関与成分が同じトクホを同時に利用した場合、摂取量によっては、結果的に1種類のトクホを過剰摂取したのと同じことになりますので、注意が必要です (1) 。
■ 専門家のアドバイスを受ける
 トクホを効果的に利用するためには、消費者自身がトクホについて正しく理解し、各々が状況に応じて必要な商品を選ぶことが大切です。しかし、巷にはさまざまな情報が溢れており、消費者が自ら正しい情報を選択することが困難な状況になっています。そのため自己判断のみで購入・利用せず、商品の成分やその機能、個人にとっての必要性、使用方法などについて理解し、正しく情報を提供できる管理栄養士や薬剤師、医師、アドバイザリースタッフ (消費者に適切に情報を提供し、消費者が気軽に相談できる者) などの専門家のアドバイスを参考にすることをおすすめします。
トクホを効果的に利用するためには、消費者自身がトクホについて正しく理解し、各々が状況に応じて必要な商品を選ぶことが大切です。しかし、巷にはさまざまな情報が溢れており、消費者が自ら正しい情報を選択することが困難な状況になっています。そのため自己判断のみで購入・利用せず、商品の成分やその機能、個人にとっての必要性、使用方法などについて理解し、正しく情報を提供できる管理栄養士や薬剤師、医師、アドバイザリースタッフ (消費者に適切に情報を提供し、消費者が気軽に相談できる者) などの専門家のアドバイスを参考にすることをおすすめします。
■ 効果的な利用法(利用する時の参考としてください)
 トクホは「いわゆる健康食品」と違い、国が製品として有効性や安全性を評価し、表示を許可した製品です。しかし、その名前が示すとおり、あくまでも「食品」です。
トクホは「いわゆる健康食品」と違い、国が製品として有効性や安全性を評価し、表示を許可した製品です。しかし、その名前が示すとおり、あくまでも「食品」です。
食生活の乱れをそのままにしてトクホを利用しても、期待する効果は得られません。トクホは現在の食生活を改善するきっかけとして、適切に利用することにより、一定の効果が得られるものといえます。
「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」という文言の表示が義務付けられているように、まずは日常の食生活を見直すことが大切です。バランスのとれた食事の中で表示通りに正しくトクホを利用することで、より一層の効果が期待できます (1)(4) 。
バランスの良い食事、望ましい食生活については、食事バランスガイドや食生活指針を参考にしてください (2)(3)(6) 。
 便秘の改善など、お腹の調子を整えるためには、以下の生活習慣が大切です。
便秘の改善など、お腹の調子を整えるためには、以下の生活習慣が大切です。①規則正しい食生活
②食物繊維を多く含む食品 (全粒穀物、野菜類、豆類、海藻類、キノコ類など) や乳製品、水分の適度な摂取
③適度な運動と休養
*食物繊維を多く含む食品を使ったメニューはこちらをご参照ください。
・トクホの特徴と利用上の注意 (効果的な利用方法)
トクホには、商品ごとに標準的な摂取量や摂取方法が記載されています。しかし、人によっては摂取目安量よりも少ない量でも、関与成分によりお腹がゆるくなるなど、体調に好ましくない変化を来たすこともあるので、体調を見ながら利用しましょう。
また、商品によってはエネルギー (カロリー) 量が高いものもあり、エネルギーの摂り過ぎにつながる可能性もありますので、効果ばかりに目を奪われるのではなく、商品全体の特徴を考慮して利用することが大切です (8)(9)(10)。
関与成分には、オリゴ糖類 (フラクトオリゴ糖、ガラクトオリゴ糖、乳果オリゴ糖、イソマルトオリゴ糖、ラクチュロースなど) 、乳酸菌・ビフィズス菌類、食物繊維 (難消化性デキストリン、サイリウム種皮、小麦ふすま) などがあります。
2.「コレステロールが高めの方に適する食品」
・トクホを利用する前に心がけましょう (基本的事項)
コレステロール値が高い人は、以下の生活習慣に気をつけましょう (11) 。

①コレステロールを多く含む食品 (卵黄・魚卵などの卵類、内臓類など) を控える
②脂肪の多い食品を控える
③食物繊維を十分に摂取する
ただし、コレステロール値は低い程良いというものではありません。血清脂質の基準値 (12) も参考にしましょう。
<血清脂質の基準値>
| LDL-コレステロール | 60~119 mg/dL |
| HDL-コレステロール | 40 mg/dL以上 |
| トリグリセリド(TG) | 30~149 mg/dL |
*食物繊維を多く含む食品を使ったメニューはこちらをご参照ください。
・トクホの特徴と利用上の注意 (効果的な利用方法)
このトクホの有効性を確認した試験では、コレステロール値が正常値よりも高く、脂質の摂取量も平均より多い人が、トクホを一定量連続して摂取した結果、コレステロール値を下げる効果が得られています。しかし、実際の食生活の中で毎日連続して同じ食品 (特にマヨネーズやマーガリンなど) を食べ続けることは考えにくく、また、トクホの種類 (油脂類) によってはコレステロール値の低下と引き換えにエネルギーを摂り過ぎてしまう可能性も否定できません (13) (14) (15) 。そのため、毎日の食事内容を見直した上で、従来の食品に置き換えてトクホを適量利用すれば、期待する効果が得られると考えられます。
関与成分には、大豆たんぱく質、キトサン、低分子化アルギン酸ナトリウム、サイリウム種皮食物繊維、植物ステロールなどがあります。
3.「食後の血糖値の上昇を緩やかにする食品」
・トクホを利用する前に心がけましょう (基本的事項)
血糖値を上げにくい食生活を心がけましょう。
①糖質の摂りすぎに気をつける
②食物繊維の多い食品を積極的に取り入れる
③食後に運動する
・トクホの特徴と利用上の注意 (効果的な利用方法)
このトクホの有効性を確認した試験では、糖質と一緒に摂取することを条件としています。そのため、糖質と一緒に摂取した際には血糖値上昇の抑制効果を期待できますが、トクホの単独摂取では関与成分がもたらす血糖上昇抑制効果は期待できません。また、食後の血糖値が上がりやすい人が、糖質を摂取する際にこれらのトクホを利用すると、期待される効果が得られるという結果は出ていますが、トクホを利用しただけで血糖値の上昇を充分に抑制出来るわけではありません (16) (17) (18) 。血糖値を上げにくい食生活や運動習慣を心がけた上でこれらのトクホを利用すれば、さらなる効果が期待できるでしょう。
関与成分には、難消化性デキストリン、グァバ茶ポリフェノール、小麦アルブミンなどがあります。
4.「血圧が高めの方に適する食品」
・トクホを利用する前に心がけましょう (基本的事項)
高血圧の原因としては遺伝的要因もありますが、トクホを利用する前に以下の点を心がけましょう (11) 。
①食塩摂取を控える
②コレステロールや脂肪の摂取を控える
③アルコールを控える
④カリウムを多く含む野菜や果物を摂取する
⑤適正体重の維持
⑥適度な運動
⑦禁煙
*食塩を控えたメニューはこちらをご参照ください。
・トクホの特徴と利用上の注意 (効果的な利用方法)
 このトクホの有効性を確認した試験では、二次性高血圧 (他の病気が原因で起こる高血圧) の人は除外し、血圧が正常値よりも高い人を対象としています (19)(20)(21)(22) 。
このトクホの有効性を確認した試験では、二次性高血圧 (他の病気が原因で起こる高血圧) の人は除外し、血圧が正常値よりも高い人を対象としています (19)(20)(21)(22) 。
日常生活の中で基本的事項を心がけることで、血圧の低下が期待できます。そのうえで補助的にトクホを利用すると、より効果が得られると考えられます。
関与成分には、杜仲葉配糖体 (ゲニポシド酸) 、ラクトトリペプチド、γ-アミノ酪酸 (ギャバ) 、酢酸などがあります。
5. 「歯の健康維持に役立つ食品」
・トクホを利用する前に心がけましょう (基本的事項)
歯の健康は全身の健康の第一歩です。むし歯を防いで、健康的な食生活を送るためには、食後の歯みがきなどのセルフケアと、規則正しい食生活、定期的な歯科検診などの習慣をつけることが大切です。
・トクホの特徴と利用上の注意 (効果的な利用方法)
このトクホの有効性を確認した試験では、一般に、1日に数回、一定時間の咀嚼を数日間繰り返した時、「むし歯の原因になりにくい」や「歯を丈夫で健康にする」、「歯ぐきの健康を保つ」などの効果が期待できるといわれています (23)(24)(25)(26) 。
関与成分には、CPP-ACP(乳たんぱく分解物)、POs-Ca(リン酸化オリゴ糖カルシウム)、カルシウムなどがあります。
6.「食後の中性脂肪が上昇しにくい食品」
・トクホを利用する前に心がけましょう (基本的事項)
このトクホは、肝臓での中性脂肪の合成や小腸からの中性脂肪の吸収を抑制することによって、食後の血中中性脂肪の上昇を抑えるといわれています。脂質の多い食事の時にこのトクホを摂取するだけでなく、食事内容を見直して脂質の摂取量を抑え、適切な栄養バランスを心がけましょう。
*食物繊維・不飽和脂肪酸が多く含まれる食品を使ったメニューはこちらをご参照ください。
・トクホの特徴と利用上の注意 (効果的な利用方法)
 このトクホの有効性を確認した試験では、食事の際に摂取することを条件としている場合があります。そのため、食事と一緒に摂取した際に中性脂肪上昇の抑制効果が期待される商品においては、食事の際に摂取する必要があり、適切な利用方法に添わなければ、トクホの関与成分がもたらす中性脂肪上昇抑制効果は期待できません (27)(28)(29) 。中性脂肪を上げにくい食生活や運動習慣を心がけた上で、これらのトクホを利用すれば、さらなる効果が期待できるでしょう。
このトクホの有効性を確認した試験では、食事の際に摂取することを条件としている場合があります。そのため、食事と一緒に摂取した際に中性脂肪上昇の抑制効果が期待される商品においては、食事の際に摂取する必要があり、適切な利用方法に添わなければ、トクホの関与成分がもたらす中性脂肪上昇抑制効果は期待できません (27)(28)(29) 。中性脂肪を上げにくい食生活や運動習慣を心がけた上で、これらのトクホを利用すれば、さらなる効果が期待できるでしょう。
関与成分には、EPA (エイコサペンタエン酸) 、DHA (ドコサヘキサエン酸) 、β-コングリシニン、難消化性デキストリン、グロビンたんぱく分解物、ウーロン茶重合ポリフェノール(ウーロンホモビスフラバンBとして)などがあります。
7.「体脂肪がつきにくい食品」
・トクホを利用する前に心がけましょう (基本的事項)
このトクホには、調理油脂類がありますが、トクホだからといって利用する量が多ければ、エネルギーの摂り過ぎにつながります。まずは食事内容を見直して脂質の摂取量を抑え、適切な栄養バランスを心がけましょう。
そのほかのタイプでは、トクホに含まれる関与成分に、エネルギーになりやすい成分や脂肪の分解・消費を促進する働きがあり、内臓脂肪の減少を助けるものがあります。
・トクホの特徴と利用上の注意 (効果的な利用方法)
このトクホの有効性を確認した試験では、トクホを含めた脂質の摂取量を同年代の平均以下に制限した上で、一般的な食品とトクホを置き換えて結果を得ています。ある試験では、試験期間中の食事はすべて栄養士が用意し、適度な運動を取り入れながら、トクホの調理油を摂取させ、同量の一般の調理油を摂取したときと比較しています。つまりバランスの取れた食生活と運動の実施をした条件で試験が行われたことがわかります。トクホであっても、その商品を食べさえすればすべての人で効果が得られるわけではないのです (5)(30) 。そのため、脂質の摂取量を控えた上で従来の食品に置き換えてトクホを適量利用すれば、効果が得られると考えられます。
関与成分には、中鎖脂肪酸、茶カテキン、コーヒー豆マンノオリゴ糖、ケルセチン配糖体、ウーロン茶重合ポリフェノール(ウーロンホモビスフラバンBとして)などがあります。
8.「骨の健康維持に役立つ食品」
・トクホを利用する前に心がけましょう (基本的事項)
骨の健康に大切なカルシウムは、摂取が難しいミネラルですが、ここ数年の国民健康・栄養調査の結果 (31) によると、閉経を迎える50代以上の女性については、40代までよりも摂取量が高くなっており、骨粗鬆症予防を意識して、積極的にカルシウム摂取を心がけている様子がうかがえます。骨の健康を維持するには、以下のようなことも気をつけましょう (11)(33) 。
①カルシウムの十分な摂取
②ビタミンD、ビタミンKの十分な摂取
③日光に当たる時間を確保する
④適度な運動負荷をかける(骨量増加のために重要)
骨の健康は一朝一夕では得られません。若いうちからの食生活や運動が、将来の骨量に影響することを意識して、骨の健康維持・増進に努めましょう (33) 。
*カルシウムが多く含まれる食品を使ったメニューはこちらをご参照ください。
・トクホの特徴と利用上の注意 (効果的な利用方法)
このトクホには、骨の形成に必要なビタミンKを多く含む商品や、骨からのカルシウム溶出を抑制する成分を含む商品などがあります (34)(35) 。
食事からのカルシウムやビタミンD、ビタミンKの十分な摂取と適度な運動に加え、このようなトクホを併用すると、骨の健康が維持できると考えられます。特に、骨の健康に支障を来たしやすい高齢者では、食事量そのものが少なく、摂取できる栄養素量も少なくなりがちです (11) 。食事や運動に併せて上手にトクホを利用しましょう。
関与成分には、ビタミンK、大豆イソフラボン、MBP (乳塩基性たんぱく質) 、ポリグルタミン酸などがあります。
9.「肌の水分を逃しにくくする食品」
・トクホを利用する前に心がけましょう (基本的事項)
皮膚には、体内の水分蒸散と微生物や化学物質などの有害物質の侵入を防ぐ役割があります。日常生活において皮膚を清潔に、健康に保つように心がけましょう。
・トクホの特徴と利用上の注意 (効果的な利用方法)
このトクホの有効性を確認した試験では、乾燥などによる肌荒れを自覚した人を対象とし、一定期間トクホを摂取した場合、経表皮水分蒸散値の低下が得られています。バランスの取れた食生活と皮膚を健康に保つことで、効果が得られると考えられます (36) 。
関与成分には、グルコシルセラミドがあります。
■ おわりに
消費者の健康志向の高まりを受けて、年々トクホの種類も多様になってきました。しかし、トクホさえ利用していれば健康になれるというわけではありません。「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」という文言の表示が義務付けられているように、まずは日常の食生活を見直すことが大切です。そして、トクホを利用する際は、利用上の注意を守って、効果的な利用を心掛けましょう。