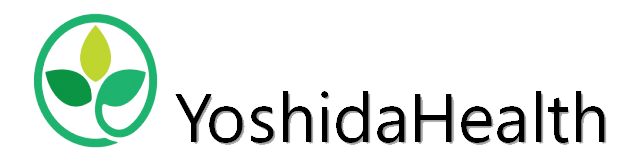A.ビタミンAとは?
ビタミンA (レチノール) は脂溶性ビタミンの1つで、主に動物性食品に含まれており、体内ではレチノール・レチナール・レチノイン酸といった3種の活性型で作用しています。ビタミンAは皮膚や粘膜の正常保持・視覚の正常化・成長および分化に関与しているため、不足すると皮膚や粘膜の乾燥・夜盲症・成長障害・胎児の奇形などを引き起こすおそれがあります (12) 。また、ビタミンAは脂溶性であることから過剰摂取にも注意が必要です。食品中には、ビタミンA以外に体内でビタミンAに変換されるプロビタミンA (ビタミンAの前駆体) というものがあります。プロビタミンAは主に植物性食品に含まれ、赤や黄色の色素であるカロテノイドがよく知られています (7) 。
B.ビタミンAの供給源になる食品

特に、β-カロテンは他のカロテノイドに比べて、効率よくレチノールに変換されます。しかし、重量あたりで見るとβ-カロテンはビタミンAの約1/12の作用しか示しません (4) 。ビタミンAを含む食品を以下の表に示しました (6) 。(可食部100 gあたり)

*バターが黄色なのは、牧草に含まれているカロテノイド色素による (10) 。
Tr (trace) ・・・微量。含まれてはいるが、成分の記載限度に達していないもの。

補足
プロビタミンAについて
生体内でビタミンA効力を示す物質に変換されるものの総称。主に小腸でビタミンAに変換されます。約600種類のカロテノイドが発見されていますが、その中でプロビタミンAは約50種類程度です (13) 。
(プロビタミンAと非プロビタミンA)

★プロビタミンAである、α-カロテンやβ-クリプトキサンチンはβ-カロテンの半分の変換率です(4)。リコピンは、プロビタミンAではありません。
★β-カロテンの吸収を高めるには、加熱料理が適していることが知られています (19) (PMID:9209178)(PMID:10801917) 。
★加工されたトマトのリコピンは、生のトマトのリコピンよりも効率よく吸収されます (PMID:9209178)(PMID:10801917) 。
C.ビタミンAの特性 (単位・化学的安定性)
今までは、レチノール、カロテンおよびビタミンA効力 (国際単位:IU) の表示を行ってきましたが、近年はビタミンA効力に代え、レチノール活性当量表示 (μgRAE) に移行する傾向があります。
ビタミンAは、酸性・酸素・光・熱に不安定で、中性やアルカリ性には安定です (12) 。
補足
レチノール活性当量の算出方法について以下に示しました
①式に従ってβ-カロテン、またα-カロテンならびにクリプトキサンチンの定量値 (μg) からβ-カロテン当量を算出し、次いで②式を用いてレチノール活性当量 (μgRAE) を算出します。β-カロテンの変換率を1/2、生物学的効力を1/6として、②式を用い、最終的にレチノール活性当量を算出し表示しています (6) 。

D.ビタミンAの吸収や働き
食事からビタミンAを摂取すると、脂質とともに小腸粘膜上皮細胞に吸収されます。一定量は肝臓に貯蔵され、他は血液によって各組織のタンパク質と結合し、組織を健全に保護する働きをしています (12) 。

β-カロテンの場合、体内でビタミンAが不足すると、必要量だけがビタミンAに変換されます。変換されないβ-カロテンは脂肪組織に蓄えられるか、または排泄されます。
生体内でのビタミンAやβ-カロテンの主な作用は、以下の図の通りです (7) (12) 。

E.ビタミンA不足の問題
ビタミンA不足による影響は?
ビタミンA不足の一番の問題は視覚障害です。ビタミンAが不足すると目の角膜や粘膜がダメージを受け、症状が悪化すると視力が落ち、失明する場合もあります (12) 。
ビタミンA不足の状況
発展途上国では、年間約35万人もの子ども達がビタミンA不足により失明しています。このような状況は、ビタミンA投与によって改善されます (13) 。
ビタミンA不足はどのように起こるの?
脂肪便症や胆道系障害などの脂質吸収不良、たんぱく質欠乏症、エネルギー欠乏症などにより、ビタミンA欠乏症が起こることがあります (12) 。また、過度のアルコール摂取は、貯蔵されているビタミンAを消耗します。しかし、健康な人は体内にレチノイドを十分貯蔵しているため、不足する危険性はほとんどありません (7) 。
F.ビタミンA過剰摂取のリスク
ビタミンAは脂溶性のため、摂り過ぎると体内に蓄積されます。過剰摂取により様々な健康被害を引き起こすおそれがあります。
ビタミンA過剰摂取のリスク
(成人がビタミンAを過剰摂取した時の主な症状)
<短期間の摂取>吐き気・頭痛・脳脊髄液の上昇・めまい・目のかすみ・筋肉協調運動障害 (4) (12) (13)
<長期間の摂取>中枢神経系への影響・肝臓の異常・骨や皮膚の変化 (12)
(子どもがビタミンAを過剰摂取した時の主な症状)
頭蓋内や骨格の異常
なお、過剰摂取による健康障害が起こる可能性がある最少量は、 成人では13,500μgRAE/日、乳児では6,000μgRAE/日です(4)。
G.ビタミンAはどのぐらい摂取すればよいの?
各年齢別のビタミンAの食事摂取基準 (日本人の食事摂取基準2015年版) は以下の通りです(4)。

1:レチノール活性当量(μgRAE)=レチノール(μg)+β-カロテン(μg)×1/12+α-カロテン(μg)×1/24+β-クリプトキサンチン(μg)×1/24+その他のプロビタミンAカロテノイド(μg)×1/24
2:プロビタミンAカロテノイドを含む。
3:プロビタミンAカロテノイドを含まない。
H.ビタミンA摂取状況
平成29年の国民健康・栄養調査では、男性では平均530μgRE/日、女性では平均510μgRE/日摂取しています (20) 。
※REはレチノール当量の略です。
I.栄養機能食品としての関連情報
ビタミンAは、栄養機能食品として表示許可されています。
・上限値は600μg、下限値は231μgです。
・ビタミンAの栄養機能表示
「ビタミンAは、夜間の視力の維持を助ける栄養素です。」
「ビタミンAは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。」
・注意喚起表示
「本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。」
「妊娠3か月以内又は妊娠を希望する女性は過剰摂取にならないように注意してください。」
栄養機能食品の表示に関する基準の詳細についてはこちらの資料をご参照ください。