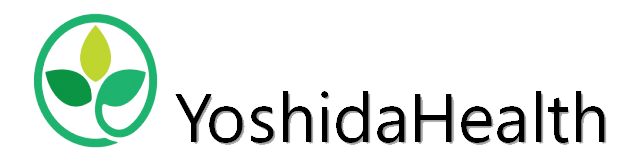Search
NameDescriptionContent
ビタミンB12解説
Source:
|
Author:構築グループ
|
Published time: 2016-12-31
|
189 Views
|
Share:
A.ビタミンB12とは?
ビタミンB12はコバルトを含むビタミンの総称で、ヒドロキソコバラミン、アデノシルコバラミン、メチルコバラミン、シアノコバラミン、スルフィトコバラミンがあります。抗悪性貧血因子として牛の肝臓中に発見されたビタミンで (12) 、微生物以外では合成されないため、植物性食品にはほとんど含まれません (3) (5) (12) 。体内では、メチルコバラミンとアデノシルコバラミンが、アミノ酸や脂質などの代謝の補酵素として働いており、不足すると悪性貧血や神経障害などが起こることが知られています (3) 。
B.ビタミンB12の供給源になる食品
主な食品のビタミンB12含有量 (シアノコバラミン相当量) は以下の通りです (5) 。(可食部100 gあたり)


C.ビタミンB12の特性 (単位・化学的安定性)
ビタミンB12は赤色を呈し、水溶性ビタミンに分類されますが、水にやや溶けにくく、エタノールに溶けにくい性質を持ちます (13)。また、中性、弱酸性には安定ですが、強酸またはアルカリ環境下では、光によって分解反応が促進されます (13) 。
D.ビタミンB12の吸収や働き
食品中のビタミンB12はたんぱく質と結合しており、経口摂取されて胃に入ると胃酸やペプシンによって遊離状態となります。遊離したビタミンB12は、胃壁細胞から分泌される糖タンパクの内因子 (IF; Intrinsic Factor) と結合し、内因子-ビタミンB12複合体となって腸管を下降し、回腸で吸収されます。吸収されたビタミンB12は、血中の輸送タンパク (トランスコバラミン) と結合し、肝臓や末梢組織・器官へ運搬されます。健康な成人における食品中ビタミンB12の吸収率はおよそ50%ですが、これは内因子 (IF) を含めた吸収機構が飽和するためで、それ以上のビタミンB12を摂取しても生理的に吸収されません。また、胆汁中には多量のビタミンB12化合物が排泄されますが、約半分は内因子 (IF) と結合できないために吸収されず、腸肝循環によって再吸収されたり、糞便へ排泄されたりします。ビタミンB12の体内での吸収は下の図の通りです (1) (12) 。

体内では、メチルコバラミンとアデノシルコバラミンが補酵素として働いています。この補酵素の働きは以下の通りです (12) 。
・メチルコバラミン・・・メチオニン合成酵素の補酵素として、ホモシステインからメチオニンへの変換を触媒する
・アデノシルコバラミン・・・メチルマロニルCoAからスクシニルCoAへの変換を触媒する
E.ビタミンB12不足の問題
ビタミンB12不足はどのような人に多く見られるの?(1) (11)
1.厳格な菜食主義者
2.高齢者など、胃酸分泌の低い人
3.胃切除者
4.小腸における吸収不全
ビタミンB12が不足すると、どのような症状が起こるの?
悪性貧血、メチルマロン酸尿症、ホモシステイン尿症、神経障害、感覚異常、記憶障害、うつ病、慢性疲労、運動時の動悸や息切れなどが知られています (12) 。

F.ビタミンB12過剰摂取のリスク
過剰に摂取しても吸収されないため、ビタミンB12の過剰摂取による障害は、ほとんどありません (1) 。
G.ビタミンB12はどのぐらい摂取すればよいか?
各年齢別のビタミンB12の食事摂取基準 (日本人の食事摂取基準2015年版) (シアノコバラミン相当量) は以下の通りです (1) 。

H.ビタミンB12摂取状況
平成29年の国民健康・栄養調査では、男性で平均6.1μg/日、女性で平均5.1μg/日であり、男女とも推奨量を充たしています (16) 。
I.栄養機能食品としての関連情報
ビタミンB12は、栄養機能食品として表示許可されています。
・上限値は60μg 下限値は0.72μgです。
・ビタミンB12の栄養機能表示
「ビタミンB12は、赤血球の形成を助ける栄養素です。」
・注意喚起
「本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。」
栄養機能食品の表示に関する基準の詳細についてはこちらの資料をご参照ください。
J.その他の情報
ビタミンB12は以下の症状の治療薬として用いられます (13) 。
1.ビタミンB12欠乏症の予防および治療
2.消耗性疾患、甲状腺機能亢進症、妊産婦、授乳婦など、ビタミンB12の需要が増大して食事からの摂取が不十分な際の補給
3.巨赤芽球貧血、広節裂頭条虫症、悪性貧血に伴う神経障害、吸収不全症候群
4.次の疾患のうち、ビタミンB12の欠乏または代謝障害が関与すると推定される場合
・栄養性及び妊娠性貧血
・胃切除後の貧血
・肝障害に伴う貧血
・放射線による白血球減少症
・神経痛
・末梢神経炎
・末梢神経麻痺
ビタミンB12はコバルトを含むビタミンの総称で、ヒドロキソコバラミン、アデノシルコバラミン、メチルコバラミン、シアノコバラミン、スルフィトコバラミンがあります。抗悪性貧血因子として牛の肝臓中に発見されたビタミンで (12) 、微生物以外では合成されないため、植物性食品にはほとんど含まれません (3) (5) (12) 。体内では、メチルコバラミンとアデノシルコバラミンが、アミノ酸や脂質などの代謝の補酵素として働いており、不足すると悪性貧血や神経障害などが起こることが知られています (3) 。
B.ビタミンB12の供給源になる食品
主な食品のビタミンB12含有量 (シアノコバラミン相当量) は以下の通りです (5) 。(可食部100 gあたり)


C.ビタミンB12の特性 (単位・化学的安定性)
ビタミンB12は赤色を呈し、水溶性ビタミンに分類されますが、水にやや溶けにくく、エタノールに溶けにくい性質を持ちます (13)。また、中性、弱酸性には安定ですが、強酸またはアルカリ環境下では、光によって分解反応が促進されます (13) 。
D.ビタミンB12の吸収や働き
食品中のビタミンB12はたんぱく質と結合しており、経口摂取されて胃に入ると胃酸やペプシンによって遊離状態となります。遊離したビタミンB12は、胃壁細胞から分泌される糖タンパクの内因子 (IF; Intrinsic Factor) と結合し、内因子-ビタミンB12複合体となって腸管を下降し、回腸で吸収されます。吸収されたビタミンB12は、血中の輸送タンパク (トランスコバラミン) と結合し、肝臓や末梢組織・器官へ運搬されます。健康な成人における食品中ビタミンB12の吸収率はおよそ50%ですが、これは内因子 (IF) を含めた吸収機構が飽和するためで、それ以上のビタミンB12を摂取しても生理的に吸収されません。また、胆汁中には多量のビタミンB12化合物が排泄されますが、約半分は内因子 (IF) と結合できないために吸収されず、腸肝循環によって再吸収されたり、糞便へ排泄されたりします。ビタミンB12の体内での吸収は下の図の通りです (1) (12) 。

体内では、メチルコバラミンとアデノシルコバラミンが補酵素として働いています。この補酵素の働きは以下の通りです (12) 。
・メチルコバラミン・・・メチオニン合成酵素の補酵素として、ホモシステインからメチオニンへの変換を触媒する
・アデノシルコバラミン・・・メチルマロニルCoAからスクシニルCoAへの変換を触媒する
E.ビタミンB12不足の問題
ビタミンB12不足はどのような人に多く見られるの?(1) (11)
1.厳格な菜食主義者
2.高齢者など、胃酸分泌の低い人
3.胃切除者
4.小腸における吸収不全
ビタミンB12が不足すると、どのような症状が起こるの?
悪性貧血、メチルマロン酸尿症、ホモシステイン尿症、神経障害、感覚異常、記憶障害、うつ病、慢性疲労、運動時の動悸や息切れなどが知られています (12) 。

F.ビタミンB12過剰摂取のリスク
過剰に摂取しても吸収されないため、ビタミンB12の過剰摂取による障害は、ほとんどありません (1) 。
G.ビタミンB12はどのぐらい摂取すればよいか?
各年齢別のビタミンB12の食事摂取基準 (日本人の食事摂取基準2015年版) (シアノコバラミン相当量) は以下の通りです (1) 。

H.ビタミンB12摂取状況
平成29年の国民健康・栄養調査では、男性で平均6.1μg/日、女性で平均5.1μg/日であり、男女とも推奨量を充たしています (16) 。
I.栄養機能食品としての関連情報
ビタミンB12は、栄養機能食品として表示許可されています。
・上限値は60μg 下限値は0.72μgです。
・ビタミンB12の栄養機能表示
「ビタミンB12は、赤血球の形成を助ける栄養素です。」
・注意喚起
「本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。」
栄養機能食品の表示に関する基準の詳細についてはこちらの資料をご参照ください。
J.その他の情報
ビタミンB12は以下の症状の治療薬として用いられます (13) 。
1.ビタミンB12欠乏症の予防および治療
2.消耗性疾患、甲状腺機能亢進症、妊産婦、授乳婦など、ビタミンB12の需要が増大して食事からの摂取が不十分な際の補給
3.巨赤芽球貧血、広節裂頭条虫症、悪性貧血に伴う神経障害、吸収不全症候群
4.次の疾患のうち、ビタミンB12の欠乏または代謝障害が関与すると推定される場合
・栄養性及び妊娠性貧血
・胃切除後の貧血
・肝障害に伴う貧血
・放射線による白血球減少症
・神経痛
・末梢神経炎
・末梢神経麻痺
© Japan Yoshida Health Research Co., Ltd. all rights reserved.